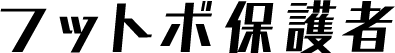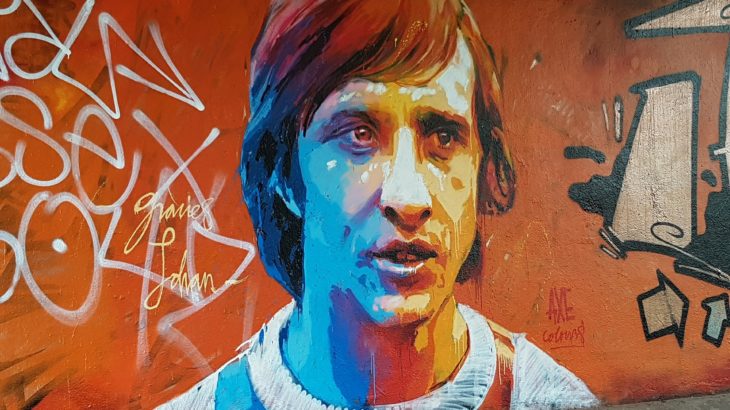子どもにサッカーをやらせていて、ある程度のレベルにまで達すると「もっと良い環境でサッカーをやらせたい」とクラブチームに移籍を考えることもあると思います。今回は実際に体験した「新小学1年生」の入団セレクションのようす、選考基準や選考内容を紹介します。
クラブチームが絶対に良いとは言い切れないですが、子どもにとってサッカーをやるのに良い環境が整っているのは間違いないです。
入団するには狭き門を突破しなければなりません。セレクションを受けようか検討している、わからないことが多くて不安な保護者の方は参考にしていただければと思います。
セレクションを受けさせるべきか本気で考え、準備する
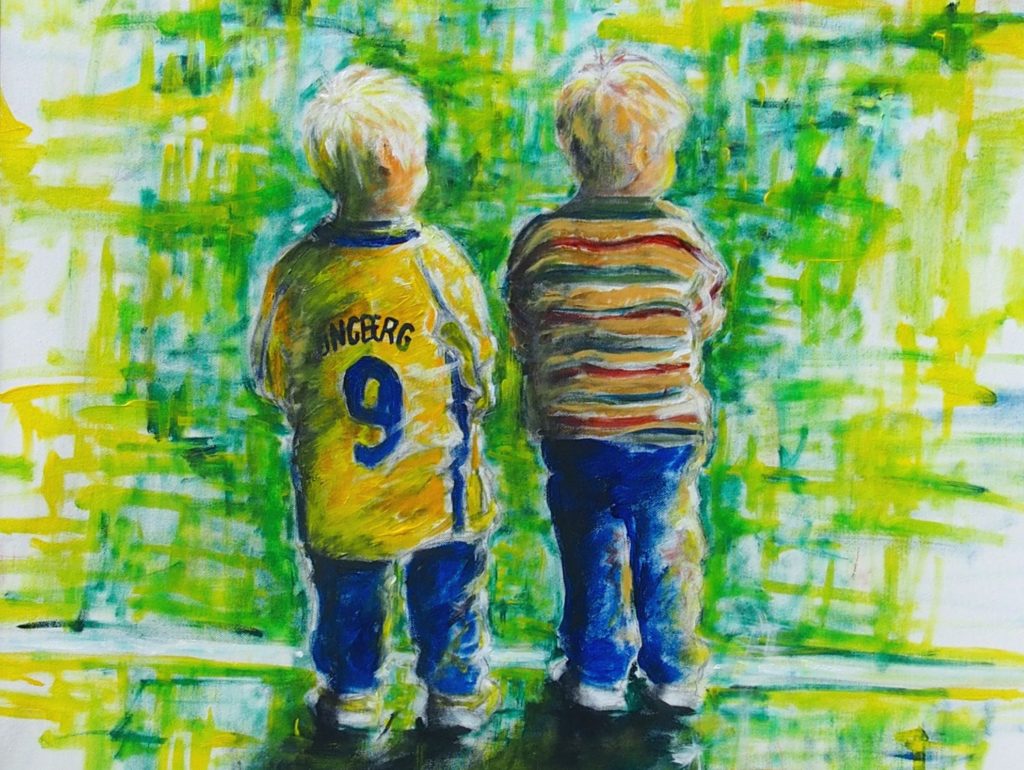
「クラブチームに入りたいからセレクションを受けたい」と子どもが自ら言ってきたら背中を押してあげるだけかもしれませんが、保護者の考えからセレクションを受けさせる場合は、子どもにとって本当に良い選択なのかしっかり検討することが大事です。
セレクションの結果によっては子どもが傷つく可能性があります。また、クラブチームに所属することで楽しくサッカーができなくなる可能性もあります。まずは、子どもがどうしたいのか耳を傾けてあげてしっかり考えましょう。
セレクションというものを子どもに説明する
私の場合は幼稚園年長というタイミングでしたので説明の仕方に工夫が必要でしたが、基本的に嘘はついてなく、大人が理解すべきことを噛み砕いて説明しました。
- 今までよりも良い環境でサッカーができる
- たくさんの子どもが受けるので合格することは難しい
- もし受かったら今の所属チームを辞めなければならないのでお友達とお別れをしなければならない
あたりを理解してもらってチャレンジする決意ができてから申し込みをしました。自分の人生の選択をしっかりしてもらいたかったからです。
セレクションに申し込む
クラブチームのWEBサイト等で指示通りに申し込みをします。大体1か月前とかに募集を開始していました。
同じ地域のクラブチーム間でセレクションの日程がぶつからないような配慮からか、毎年同じような日程でやっているみたいです。
目的のクラブチームの過去の情報を探せば、おおまかな日程を事前に把握することができます。セレクションの回数と時期ですが、新1年生は年に1回冬のシーズンというクラブチームでした。
申し込み自体はそこまで難しくありません。「名前」「連絡先」のようなA4におさまる程度の一般的な内容です。少し特殊なのは「保護者の身長」「保護者のスポーツ歴」がありました。
現在所属しているチームに同意書を書いてもらう
書類はセレクション申込ページにPDF等で準備されていてダウンロードできます。コーチや監督でなく、所属チームの代表者にサインをもらう必要がありますので、手元に来るのに少し時間がかかると思います。
同意書は事前にトラブルを防止するためという意味があります。未所属とウソをついてセレクションを受けて、せっかく合格したのに現所属チームとトラブルになって退団がスムーズにできないという話も聞いたことがあります。
チャレンジすることを応援してくれたら良いですが、『今まで育ててきたのに…』と嫌な顔をされる可能性もあります。所属チームに説明するというのは保護者にとって意外と大きな仕事となってきます。セレクションを受けるだけでも覚悟が必要になってきます。
セレクション当日のための準備
子どもはサッカーができる服装、サッカーボール、水筒程度で特別な準備はしなくて大丈夫です。クラブの指示通りに準備すれば問題ないです。
保護者は、遅刻しないように移動のシミュレーション、おつりが出ないようにセレクション費用を準備、ビデオカメラとか当たり前な物あたりになってくるでしょう。沢山の人が集まりますので、多少の雨だったら決行する可能性が高いです。子どもも保護者も悪天候時の準備はしておいた方が良いでしょう。
1次セレクション当日のようす
受付で名前を伝えると番号入りのビブス(ゼッケン)が渡されました。色と番号で個人を判別するためです。その後は開始時間まで自由にボールをけっていました。
選考内容
全員で鬼ごっこのようなウォーミングアップを軽くして、その後はひたすらフットサルコートで10分弱の10人対10人ぐらいのゲームを繰り返しました。
受験者は100人以上はいるみたいでしたので、評価をするコーチも20人近くいて各コートをローテーションで見て回っているようでした。
まだ幼稚園年長で、回りは知らない子ばかりですしパスという概念は無く、ひたすらボールの取り合いをして団子サッカーをしていました。
どうやって評価をするのか疑問に思っていましたが、団子サッカーの中でも目立つ子はやっぱりいて「こういう子が受かるんだろうな」と感じる瞬間がありました。あの団子サッカーを見ると「もしかしたら一度もボールを触っていない子がいるのではないか?」と思うぐらいでした。
セレクションの選考基準と結果発表
5ゲーム程でセレクションは終わり、子ども達を集めてクールダウンをしている間に保護者を集めて説明がありました。結果は1週間ほどで郵送する、2次セレクションの日程は郵送物に含むなどの簡単な説明がありました。
「幼稚園年長に合否をつけるのは本当に難しい。今回の結果がすべてではないので、またチャレンジをして欲しい」という話がありました。これには全く同じ意見です。
たった数時間のゲームでその子の将来を判断するなんて無理です。もし良い結果が出なくても、このことは保護者がしっかり理解して子どものケアをしてあげて欲しいです。
セレクションで何を見ていたかの話もありました「走れるか」「ドリブルできるか」「ボールを求めているか」とか当たり前な感じの評価基準でした。点を取ることも重要ですが、それよりも基礎的な部分を見ている印象でしたので、まずボールを触ることが重要かなと思います。
2次セレクション当日のようす
ベースは1次セレクションと同じです。2次セレクションは「1対1」「2対2」「25m走のタイム」「ゲーム」という、よりサッカースキルを見るような内容となっていました。この日も2時間程度で、少ない人数を大勢のコーチでしっかり見ている印象でした。
1次セレクションを通過しているだけあって、皆サッカーのベースがあるようでした。セレクションの内容的にも個人の勝敗がハッキリする内容ですので、アピールするにはやっぱり勝つことが大事になってくると思います。
目立つ子はやっぱりいて、足元の上手さ、スピード、パワー、ボールへの執着心など素人が見ても違いが分かるレベルでした。
選考基準と結果発表は1次セレクションと同じで、当日体調不良でこれなかった子や、もう一度見たい子のために3次セレクションもあるとのことでした。
まとめ
- セレクションというものを子どもも保護者も理解する
- 申し込みや準備に「同意書」がかかわってくることもある
- 当日は楽しくサッカーをするだけ。もし落ちても次チャレンジすればよい
今回は「新小学1年生」というピンポイントなタイミングのセレクションのご紹介でしたが、参考になれば幸いです。このセレクションでは十数人が合格し新チームが結成されましたので、合格のチャンスは大きかったのかもしれません。
上手ければレギュラーがとれる世界でもありますので、セレクションで合格できるチャンスはいつでもあるとも言えます。クラブチームを目指している子の保護者は、いつかセレクションで合格できるように長い目線での応援とサポートが重要だと思います。