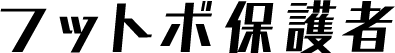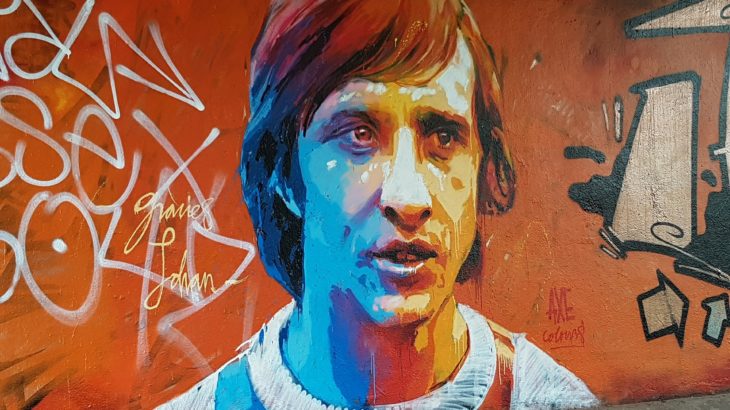息子のチームはどちらかと言うと試合が多いです。県をまたいで遠征することもあり、トレーニングマッチや大会で試合が無い月はほとんど無いです。
練習より試合ばかりして上手くなるのか?と疑問に思うことがあったので、今回は保護者目線で試合ばかりの子どもが上手くなるのかまとめてみたいと思います。
子どもの学習能力が高かったりチームの状況次第では試合をした方が上手くなるが、練習もやっぱり大切

試合を重ねた方が色々な成功や失敗の経験できて成長につながるのは間違いないと思います。時には爆発的な成長があるでしょう。
ただ、子どもが試合の経験をすべて吸収して効率よく成長していけるかというと、そうでもないと思います。みんな個性があり学習能力が違うので同じ成長曲線にはなりませんし、良い時と悪い時の波があるのが息子だけでなくチームメイトを見ても感じ取れます。
練習も大切でチームとして学ぶこと、個人の課題のための自主練はやっぱり必要です。チームの方針でモヤモヤする時、保護者はどうすべきでしょうか。
試合が多いチームの保護者の心構え
チームが試合経験から学ばせる方針の場合、基本的には保護者が介入するのはなるべく避けた方が良いと思います。せっかく子どもが自分から成長していく環境を準備しているのに崩してしまいます。
チームから保護者に対して介入しないように明確に言われることもあり、大会で応援が禁止されてたり、妙に大人しい保護者が多いチームは子ども主体の方針が徹底されているということです。
基本は子どもの成長を待つ
何でも答えを教えるのではなく自分で考える能力を高め人間力をあげるために待ちましょう。
口を出したくなりますが我慢が必要です。もし出すのであれば、その答えに導く投げかけや、子どもがすんなり納得できるような話し方が良いでしょう。
試合の勝ち負けを気にしない
とても難しいですが、気にしてたら気が滅入るだけです。トレーニングマッチは名前の通り練習ですし、大会の試合も将来のための経験です。
大人が勝ちにこだわり過ぎて、勝ち方を徹底的に教え込んでるチームもあったりします。そういうチームは脆いもので、失点したら大量失点で負けたりします。
子どもが自分で考え行動する事が大切です。保護者が勝ちたい気持ちは抑え込みましょう。
自主練やビデオ反省など、やるべきタイミングにはやるように促す
試合での経験から爆発的な成長を待つのもひとつですが、やるべき事はしっかりやるべきだと思います。
チームの練習が少ないのは練習しなくて良いという意味ではなく、各々やるべき事はやってきてねという意味です。
練習メニューや、反省の内容は何でも良いと思います。サッカーに向き合うタイミングには、しっかりと集中して向き合うように促してあげれば良いと思います。
練習のやり過ぎも問題ですので、その辺はコントロールしてあげた方が良いでしょう。
普通のサポートを当たり前のようにする
試合当日のお弁当や水筒、ゼリーなどの軽食など子どもが試合に集中できる環境づくりを手伝ってあげましょう。
ただ、間違えてはいけないのは手伝い過ぎはダメです。ある程度の年齢になったら練習や試合の準備は自分にやらせて自立させていかなければなりません。あくまでもサポートです。
どういう弁当が良いのか意見を聞いたり、忘れ物のチェックをするように促したりなどです。
子どもの成長を待てない、なるべく早く改善したい場合
今チーム内でAチームとBチームの境目にいたり、セレクションを受けたいと考えている方はやっぱり早く改善したいと思うかもしれませんしれません。
保護者が介入しない形でおすすめなのは、週1でも子どもに本当に合ったスクールに入れる事だと思います。
- ボールコーディネーションなど基礎中心
- 長所を伸ばす
- 短所を改善する
- 子どものやる気や勇気を引き出すコーチがいる
- 全く別のスポーツをしてみる
子ども主体で自分から成長してもらう方針は変わらないですが、爆発的な成長のために起爆剤となるものがあると良いかと思います。
イメージとしては掛け算での成長となるものです。なので子どもに本当に合った選択が必要だと思います。
「有名なスクールだから」「ドリブラーになって欲しいからドリブル特化」等の選択ではなく、試合経験での成長を最大化できる材料を検討するのが良いと思います。
おすすめなのは、ボールコーディネーションなど基礎中心のスクールだと思います。ボールをうまく蹴れるだけで世界が変わってきます。目に見える結果が出るのに少し時間がかかるかもしれませんが、週1回で2ヶ月〜3ヶ月やれば変化が見えてくると思います。
何でも良いので、子どもが楽しく通えて、何かしらの能力が伸びる時間を作ってみることをおすすめします。
息子にはあえてテレビゲームをやらせてます。勝負感や賢さを身に付けて欲しいからです。
J下部は試合で成長させる方針のよう
トレーニングマッチや大会で対戦することが多いのですが、試合中の声の掛け方やチームの完成度を見ていると試合で成長させるタイプのチームが多いと感じました。また、保護者の介入をコントロールしているようで試合会場に保護者がいない時もありました。J下部を目指している方は理解していたほうが良いと思います。
- 試合中に声を掛けることは少な目
- 今のはどうだったか?等、疑問を投げかける
- 勝ち負けにこだわらず、経験させる事に注力している様子
- 怒ることがほとんど無い
JFAの育成ガイドラインに沿ったものをどこもやられている印象です。
良く言えば、自分で成長していくことを促す理想的な育成で、子どもがサッカーを楽しみながら経験から成長できるやり方だと思います。
悪く言えば、成長を子どもに丸投げしているとも解釈できるので、自分から成長できないと置いていかれる可能性があると思います。
J下部のアカデミーからジュニアユースへの昇格率はそんなに高くない
各チームや年代によってバラツキがあるとは思いますが、大体50%〜70%位の昇格率だと思います。
この数字をどう見るかは個人の感覚になってくると思いますが、私は低いかなと思います。
J下部は天才を待っているのかもしれない
ユースからトップチームへの昇格ではどうでしょうか。ユースからあげずに強豪高校からスカウトしてトップチームに登録することも結構あります。
J下部としては沢山の子どもたちを引き上げる必要はなく、上にあげていく数人が発生する為のやり方をしているのではないでしょうか。
なので、試合経験から学ぶ育成は良い面もありますが、しっかりとついて行かないと置いてかれてしまい子どもにとって難しい状況になってしまう可能性があります。
まとめ
練習をしないで試合で勝ち負けを繰り返していると不安なってくると思います。しかし、保護者はここは我慢して長い目線で行動していかなければなりません。
保護者がやる事は、試合での経験を最大化できるサポートです。サッカーだけでなく大人になるための成長をきっとしてくれています。
何が合っていて何が合っていないのか判断できるよう、常にサポートできる位置で子どもを見守っていきましょう。
子どもの成長についての記事はこちらから。
コーチングとティーチングの違い